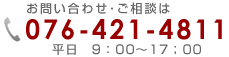決議文・意見書・会長声明
地方消費者行政の維持・強化を求める会長声明
2025.04.30
第1.声明の趣旨
当会は、国会及び政府に対して、消費者被害を防止・救済するため、地方消費者行政に関し、次のことを要請する。
- 地方自治体の財政事情によることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための恒久的な財源を措置すること。
- 消費生活相談員が安定的に業務を継続できるよう、その専門性に見合う処遇を確保するための制度設計と必要な予算措置を講じること。
- 国が進める消費生活相談のデジタル化にかかる予算、特にPIO-NETの刷新や運用により地方公共団体に生じる費用を国の責任で措置すること。
第2.声明の理由
- 令和6年版消費者白書によれば、2023年の全国の消費生活相談件数は約90.9万件であって前年度よりも3万件以上増加した。同白書による同年の消費者被害・トラブル額の推計値のうち、契約購入金額は約10.6兆円、既支払額(信用供与を含む)は約8.8兆円であり、いずれも前年より2兆円以上増加している。また、富山県消費生活センターが発表した「令和5年度 富山県消費生活センターにおける消費生活相談の概要」によれば、同年度に同センターに寄せられた相談件数は4945件であり、高水準を保っている。
このように、消費者被害は依然として深刻な状況であり、これらの消費者被害を救済し、被害を未然に防止するためには、住民が身近な自治体において相談ができる体制の整備・拡充や消費者教育・啓発、地域での連携といった地方消費者行政の充実・強化が不可欠である。 - しかしながら、国が地方消費者行政に対して措置する交付金の予算額は消費者庁創設時に比べ大幅に減額されている。また、現行の地方消費者行政強化交付金のうち、消費生活相談員の人件費にも活用可能な地方消費者行政推進事業の活用期間は、全国的に活用期限が迫っており、2025年度末をもって多くの地方公共団体で終了時期を迎える。
国による財源的支援がなくなれば、自治体の自主財源による負担が増加し、限られた予算のもとでの人材確保は、ますます難しくなることが想定される。このような状況では、消費生活相談員の減員や相談日・相談時間の削減は避けられず、地方における消費者被害の件数や被害額がますます増加することが懸念される。一方で、従前の相談体制を維持しようとする場合、消費者教育・啓発等に充てていた予算を相談体制に関する予算に充てざるを得ず、いずれにしても、地方消費者行政全体として、大きく後退を余儀なくされる結果となる。
したがって、国は、消費生活相談員の人件費にも活用できるこれまでの交付金措置を2026年度以降も継続的に実施しつつ、この問題の抜本的な解決のために、従来のような期限付きの交付金措置ではなく、地方財政法第10条の改正により国がその全部又は相当割合を将来にわたって恒久的に負担する仕組みを検討する等、地方自治体の財政事情によることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための恒久的な財源を措置すべきである。 - また、近年、消費生活相談員の高齢化と、新規・若手の成り手が少ないことによる担い手不足も大きな問題となっている。その背景には、相談員の専門性の高い業務内容に見合う処遇が確保されていないことがあると指摘されている。
そこで、消費生活相談の最前線で対応している消費生活相談員が安定的に業務を継続できるよう処遇の改善が必要であるとともに、相談員の高度な専門性に見合った専門職任用制度の在り方を検討する等、制度設計と国による予算措置が必要である。 - さらに、消費者庁は、消費生活相談のデジタル化を利用したサービス向上への体制再構築を推進するとして、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)を刷新し、消費者向けウェブサイトや相談支援システム、相談分析、情報提供システムなどシステム基盤の整備を行うという計画を進めている。
このうち、消費生活相談のデジタル対応を行うための体制整備については、今のところ、地方消費者行政強化交付金の対象経費となっているものの、PIO-NETの刷新やシステム利用のための体制整備に必要な全ての経費を交付金でまかなうことができるわけではなく、その一部を、地方公共団体の自主財源により支出する必要がある。しかし、国が進める消費生活相談のデジタル化にかかる予算は、本来、すべて国の責任で措置すべきである。
また、PIO-NETに登録される情報は、相談現場における助言・あっせんのための情報としての役割以外に、法執行の端緒や立法政策の根拠ともなるものであり、全国的に被害情報収集・集約をすることが国の消費者行政施策にも不可欠である。
このようにPIO-NETは、国の推進する消費生活相談のデジタル化施策であり、国の消費者行政施策上も不可欠のシステムでもあるのだから、消費生活相談情報を全国一律に一元的に集約し活用する仕組みが維持できるよう、その刷新や運用の費用は、すべて国において負担すべきである。 - 以上の点については、政府が2025年3月18日に閣議決定した「第5期消費者基本計画」の中にも「地方消費者行政の推進」として、一部言及があるところではあるが、上記のとおり、地方公共団体における消費生活相談体制が維持できなくなるおそれがあるという現下の深刻な事態に鑑み、具体的かつ実効性ある施策を速やかに展開すべきである
2025(令和7)年4月24日
富山県弁護士会 会長 片 岡 長 司